犬はどれだけの寒さに耐えられるのでしょうか。
室外飼育をされている方だけでなく、室内飼育をされている方もお散歩中の凍傷など心配になってしまうことがあると思います。
今回は犬の寒さの耐性について紹介したいと思います。
Contents
犬は寒さに強いのか?
基本的に犬は寒さに強い生き物です。
しかし、犬種や個体間で「寒さに強い、弱い」という差は存在しています。
犬種間で寒さへの耐性に差ができる大きな要因の1つに「被毛の種類」があります。
- オーバーコート
- 皮膚を保護する為に生えている固く太い毛です。上毛、トップコートと呼ばれることもあります。
- アンダーコート
- 主に保温を目的とした綿のような柔らかい毛です。下毛と呼ばれることもあります。

生えている毛の種類によって以下のような毛種の変化にも繋がる事を覚えておきましょう。
【シングルコート】
オーバーコートがしっかりと生えており、防寒に役立つアンダーコートが少ない種類です。
抜け毛が少なくなるようにと改良されたことにより生まれた種類であり、抜け毛が減ることで手入れが楽な特徴がありますが防寒性が弱いです。
【ダブルコート】
オーバーコートだけでなくアンダーコートもしっかりと生えている種類です。
シングルコートに比べ毛量が多い為、体温を逃しにくい特徴があります。
換毛期と呼ばれる毛の生え変わりがあり、ブラッシング等の手入れが増えますが寒い冬にも耐えられます。
本来イヌ科動物はダブルコートの生物ですが、人間が室内飼育をするために抜け毛が少なく手入れが楽なシングルコートの犬種を作り出しました。
室内飼育で室温を保ち続けている家庭であれば、日常生活では問題ありませんが冬季のお散歩など外に出る機会がある際に極端に寒さに弱くなってしまいます。
また被毛だけでなく体格の違いも寒さへの耐性に大きく影響します。
体が大きいと体重あたりの体表面積が小さくなり、熱を逃しづらいのです。
その為、寒冷地に生息する動物の体が大型である傾向は犬だけでなく生物全体に共通します。
ホッキョクグマがわかりやすいですね。
体を大きくすることで、寒さへの耐性を高めているのです。
従ってダブルコートの大型犬は基本的に寒さに強く、シングルコートの小型犬は寒さに弱いという傾向があります。

大きさも耐寒性に大きく関係するという事を覚えておこう!
寒さに強い犬種
- ラブラドール・レトリーバー
- ゴールデン・レトリーバー
- シベリアン・ハスキー
- バーニーズ・マウンテン・ドッグ
- 柴
- 秋田
- 日本スピッツ
寒さに弱い犬種
- チワワ
- トイ・プードル
- ヨークシャー・テリア
- ミニチュア・ピンシャー
- イタリアン・グレーハウンド
寒さに対して弱くなる要因

上にご紹介した寒さに強い犬種であっても、その犬の状態によっては寒さに弱くなってしまうこともあります。
以下に、その主な要因をご紹介します。
【年齢】
幼犬や老犬は健康な成犬に比べ体温の調節機能が不十分であり、寒さに弱いです。
(暑さにも弱いです。)
犬の平均体温はおおよそ37.5度から39.0度とされます。
小型犬では高めの傾向があり、38度以上を基準とする考えもあります。
寒そうに凍えている時の体温を測っておくと、愛犬の体調管理に繋がります。
【生活環境】
室内飼育で暮らしている犬は、寒さに弱い事があります。
時には換毛がうまく行われておらず、いわゆる冬毛に切り替えられていないこともあります。
【病気】
甲状腺機能低下症という病気や、全身の状態を悪化させる何らかの病気にかかっていると、代謝が低下し熱を産生する能力が弱まります。
熱を生産する能力が低下すると、体温の維持が難しくなり寒さに弱くなります。
冬のお散歩は凍傷に注意しよう

冬季のお散歩は外気によっては、寒さに強い犬であっても凍傷になってしまうことがあります。
凍傷とは、身体の一部の温度が極端に下がってしまった場合に血管が収縮して血液が巡らなくなることや、凍結によるダメージによってその部分が壊死してしまう状態です。
凍傷になりやすい部位は体の末端(四肢の先端、耳、尻尾など)です。
ただし、犬の場合には肉球を含めた四肢の先端は凍傷になりづらいと言われている為、あまり神経質にならなくても大丈夫です。
※犬の肉球は冷たい地面の上でも血液循環を行うことにより一定時間、凍傷を防ぐことが出来るそうです。
参考:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1365-3164.2011.00976.x
しかし、だからといって凍傷に絶対にならないということではありません。
何度以下から凍傷のリスクがでてくるかという明確な基準はありません。
過剰に心配する必要はありませんが、北海道や東北などの寒冷地では少なくとも凍結した路面を長時間散歩するようなことは避けたほうが無難でしょう。
凍傷以外に、融雪剤によるダメージや転倒などのリスクも考えられます。
また耳や尻尾には、肉球ほどの寒さ耐性はありません。
ビーグルのような耳が薄く、広い犬種では特に耳の凍傷に注意が必要です。
最近ではさまざまな犬用の防寒グッズが市販されているので、それらを利用するのがよいでしょう。
凍傷の初期症状
耳や尻尾の皮膚は凍傷になりやすい部位なので、特に注意して観察しましょう。
毛に覆われていてわかりづらいこともあるため、実際に手で触れてみて皮膚の温度を確認したり、毛をかきわけて観察したりするとより安心です。
【変色】
[白色] → [赤色] → [黒色]
色が黒に近づけば近づく程、凍傷の度合いは酷くなります。
黒くなると最悪の場合壊死している可能性があります。
観察を怠らず、犬の凍傷に気づくことが出来るようにしましょう。
【水疱(水ぶくれ)】
変色後、適切な処置が行われないと皮膚が膨れ上がり水疱が出来ます。
程度が著しい場合には筋肉や骨まで壊死してしまい、切断が必要になる事もあります。
室内の温度は何度に保てばよい?暖房は必要?
室内飼育をしている場合に悩むのは、室内の温度ではないでしょうか。
家族が一緒にいる場合にはいいとして、留守の間も暖房は必要なのでしょうか。
こちらで参考に出来そうなデータを紹介したいと思います。
米国で発表されたデータによれば、小型犬および中型犬は4度以下、大型犬は1度以下から注意が必要とされます。
個体差もあるためこの基準がすべてではありませんが、ひとつの目安とはなるのではないでしょうか。
そうすると、留守中には室温が少なくとも4度(大型犬なら1度)を下回らないように注意する必要があります。
寒冷地での暖房器具はエアコンあるいは石油ストーブが多いかと思います。
エアコンであれば、電気代さえ容認できれば留守中にも稼働させることは可能でしょう。
しかし、石油ストーブは換気の問題や火の用心の観点から留守中に稼働させることは難しいかと思います。
室内全体を暖かく保つことが難しい場合には、部屋の一部に犬が暖をとれる場所を確保しましょう。
そのために利用できる暖房器具はペット用ヒーターや湯たんぽが考えられます。
それらに併せて、フリース素材などの保温性の高い毛布を用意したり、洋服を着せたりすると凍傷や低体温症を防ぐことに繋がります。
寒い冬を乗り越える為に、獣医からの一言
寒い冬、犬がどれだけの寒さを感じているのかは気になるところですよね。
今回の記事では、凍傷や低体温症などを防ぐための目安をご紹介できたかと思います。
この目安を利用しつつ、普段から様子をよく観察してあげてください。
震えたりジッとしていたり、人にやたらと寄ってきたり。
寒さを感じた犬が見せるサインは様々ですので、普段と違う様子を見逃さないようにできるとよいですね。
それが凍傷や低体温症のいちばんの予防法でもあります。
寒い冬も犬と一緒に楽しみつつ乗り越えていってくださいね。



















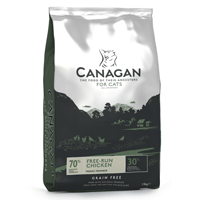




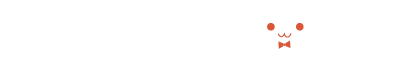
ちなみに犬だけでなく猫にも同様の毛が生えているよ!